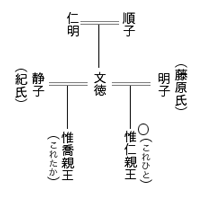|
|
|
|
|
|
|
小野小町
〜神秘のとばりに包まれた伝説の美女の謎〜
|
|
|
* 不可解な小町のイメージ * |
|
|
| 小野小町ほど、有名でありながら、謎に包まれている女性はいないだろう。歴史に全く興味のない人でも、百人一首に載っている彼女の歌と名前くらいは知っている。彼女は、美人の代名詞のように例えられ、楊貴妃、クレオパトラとともに、世界の三大美人とも呼ばれているぐらいである。
|
|
|
しかし、実際のところ、彼女が平安時代前期(9世紀の中頃)の女流歌人であり、六歌仙、36歌仙の一人に選ばれているということがわかっているぐらいで、その出生も、生い立ちも正確なことは、何一つわかっていないのが事実なのである。 |
|
| また、彼女の名前も不明である。小町は彼女の名前などではない。では、小町とは何なのか。それは役職や官位などをあらわす記号のようなものなのである。
平安時代、女性は実名では呼ばれず、父や夫の役職名で呼ばれることが多かった。例えば小野小町よりは、150年ほど後に宮仕えをした枕草子の作者、清少納言は、父の清原元輔が少納言であったため、清と少納言の二字を取って、清少納言と呼ばれるようになったのである。源氏物語の作者、紫式部の場合も、父は藤原為時という文人で、役職は式部だったことから、清少納言の場合と同じく、藤式部と呼ばれていたようだ。ところがその後、彼女が源氏物語を書き出し、その中で「紫の上」を書いたあたりから、いつの間にか紫式部と呼ばれるようになったらしい。
|
|
 |
|
|
|
|
| そういう意味で、小野小町も、小野氏の娘であったと考えられている。 |
|
| 小野氏は遣隋使で有名な小野妹子(おののいもこ)を祖先とする中級の貴族だった。 |
|
| 京都、山科の隨心院(ずいしんいん)の近くには、小野の里と呼ばれる場所があり、小野一族のゆかりの地が今でも残っている。 |
|
|
随心院、小野小町の邸宅跡とも、彼女が晩年住んだ場所とも言われる。 |
|
|
|
| 彼女が小町と呼ばれていたということは、要するに、天皇の後宮である更衣だった可能性が高いと考えられている。天皇の妻は、皇后・中宮・妃・女御・更衣という順に位があったが、女御までは殿舎が与えられたが、後宮の中でも、一番身分の低い更衣は、常寧殿(じょうねいでん)という建物の中を屏風や几帳などで、簡単に仕切って、その区画を与えられていたに過ぎなかった。長方形に仕切られた部屋のことを町(まち)と言っていたので、それが小町と呼ばれるようになったゆえんであろう。 |
|
|
続日本後記には、平安前期の承和9年(842年)、仁明(にんみょう)天皇の後宮で、正六位上に任じられた小野吉子(きちこ)という女性が記録されているが、小野吉子は、更衣の位であったことから、彼女こそが、小野小町だったと考える説もある。あるいは、彼女には、姉がいたらしいから、吉子の妹だと言う意味で小町と呼ばれたとも考えられる。恐らく、小野小町はこの吉子本人か、もしくはその妹だったと考えてほぼ間違いないように思う。
|
|
| しかし、わかるのもそれくらいで、全く彼女ほど、実像のわからぬ人物も珍しいと言えるのではないだろうか。伝説が一人歩きをして、実像を越えた典型的な人物なのである。 では、どうして、そのような伝説、とりわけ、小野小町が、絶世の美女だったという伝説が、確定的な証拠もないのに後世に付け加えられることになったのだろうか? |
|
|
|
* 全国各地に伝わる小町伝説 * |
|
|
|
| 彼女には、全国各地に絶世の美女であったという小町美人伝説やそれにまつわる数々の逸話がたくさん残されている。 |
|
| 一説には、彼女は、 出羽の国(秋田、山形の間)に生まれたという。たいそう美しい娘だった彼女は、13歳にして京へのぼり、都の風習や教養を身につけ、その後20年間、宮中に出仕した。彼女は、また非常な美人で、その才女ぶりは、あまたの女官中並ぶものがないといわれ、それゆえ、数多くの男性から求婚されたが、彼女は応じることなく、かたくなに拒み続けたというのだ。宮仕えをやめてからは、世を避け、ひっそりと香を焚きながら92歳で天寿を全うしたと言うのである。
|
|
| また別な説では、小野小町は若い頃の絶頂期の栄華に比して、その晩年はあまりにも不幸であったかのように描かれている。多くの男性の誘いを断り続けるうちに、次々と親兄弟に先立たれて、権力の後ろ立てを失って一人になってしまった彼女は、急速に没落してゆく。そして、あれだけ美しかった容貌も、見る影もなくやつれ果ててしまうのである。 |
|
|
| 誰にも見向きもされなくなった彼女は、仕方なく、猟師の妻となるが、それも、夫や子供に先立たれてしまい、最後には、乞食となって地方を徘徊するというのである。とんでもなく壮絶な話だが、こういったストーリーが作られたのは、5百年ほど経った後世になってからでいずれも真実ではない。 |
|
|
では、小町の美しさや彼女の性格を物語る有名な逸話の一つ、深草少将の百夜通いの話はどうであろうか? |
|
|
| 彼女は、多くの男性から求婚されたが、なかでも、とりわけ熱心だったのが小町の美しさに魂を奪われた深草少将(ふかくさのしょうしょう)だった。彼は小町に執拗に愛を強要するが、途方に暮れた小町は、仕方なく百夜、私のもとに通い詰め、満願となった時、晴れて契りをむすびましょうと約束したのである。
少将の屋敷から、小町の屋敷までは、やや傾斜気味の登り道が約6キロほどあり、歩けば1時間半くらいはかかる距離だが、毎夜通うとなれば、かなりの忍耐を必要とする。しかも4位の少将は、昼間は多忙の身でもあった。だが、小町の心を得たい一心で、少将は恋文を持って、この地道で辛い百夜通いを開始した。くる日もくる日も、雨の日も嵐の夜も黙々と通い詰め、睡眠不足に悩まされながらも、99日までがんばった少将であったが、最後の晩、ついに過労と大雪のため力尽き、途中で凍死してしまうのであった。
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| 京都の山科には、今も、深草少将が小町のもとへ百夜通いしたという通い道が残っている。 |
|
| あと少しで念願が達成出来たはずの気の毒な限りの少将だが、しかし、この深草少将は実在の人物ではない。 |
|
|
つまり、後世の人が、小町の美人伝説を強調するあまり、勝手につくりあげた逸話に過ぎないのである。 |
|
|
小町が男たちの恋文を埋めたと言われる塚(随心院) |
|
|
|
* 小町の生きた時代 * |
|
|
| ところで、小野小町が生きた平安時代初期はどういう時代であったのだろう?
桓武天皇が794年に平安京に都をかまえて、平安時代が到来するが、この頃はまだ奈良時代の面影を色濃く受け継いでいた。つまり、中国、唐の影響が色濃く見られていた時代で、王朝絵巻に登場する貴族や十二単を着て長い髪に扇をかざして、牛車に乗った女御というイメージになるのはまだ百年以上も先の話である。つまり、平安初期(9世紀の中頃)の宮廷女性の服装は高松塚古墳の壁画に見られるような天女のような恰好をしていたのである。
|
|
|
ヘアスタイルにしても、髪上げをして、髪の毛を頭の上で束ねて結髪をするという感じであった。眉は我眉(がび)と言って我の触覚のような形をした眉を引いていた。化粧にしても、ほお紅と口紅をつけていたぐらいで、顔全体にお白いを塗りたくる習慣などはなかったと思われる。衣裳は、裳(も)と呼ばれる色とりどりの縦じま入りのスカートを履き、カラフルな絹の上衣を着て、その上から細い紐で結んでいたようだ。手には長い柄のついた団扇のようなものや如意(にょい、ワラビ形をした30センチほどの用具)を持っていたのである。 |
|
 |
|
|
|
|
|
| この、言わば、天平スタイルと呼ばれる服装が、当時のトップモードであり、当時の人々の羨望の的であった。 |
|
|
この頃の貴族が、いかに当時の先進国、唐の文化に強いあこがれを抱き、意識していたか伺い知れるところである。 |
|
| 百人一首のかるたなどで描かれる小野小町は、十二単を着て長い髪の姿の美人画で知られているが、これは鎌倉時代(13世紀)に描かれた佐竹本36歌仙の絵姿による影響によるもので、実際の小野小町は天女のような服装で宮仕えをしていたと思われている。 |
|
|
|
飛鳥・白鳳時代の仏像、真耶夫人像。インドの仏教美術は、中国、朝鮮と伝わる過程で、中国的な特徴に変化する。小野小町も、このような服装をしていたに違いない。 |
|
|
|
食生活にしても、中国文化の影響を受けて、動物や魚の肉を焼いたり蒸したり油で加工したりして様々の調理方法が誕生した。調味料は塩、酢、油の他、バターや牛乳なども使われていたようだ。 |
|
|
|
* 病的な平安中期の美人像 * |
|
|
|
|
| 思えば、この当時の貴族はまだ健康的な生活を送っていた。ところが150年ほど経った平安の中期頃になると、中国文化の影響を脱して、日本的な特色が多く見られるようになる。しかしそれは、皮肉にも非健康的で非衛生的な方向としか言いようのないものであった。食生活は豪華だが塩辛い干し物中心になり新鮮な野菜などは取らない。それに加えて、日がな一日、部屋に閉じこもって体を動かすこともない。こうして、運動不足も加わり極めて不健康で病的なものになってゆくのだ。 |
|
| 貴族の顔色はいつも病的に青白く、それを意識してかどうか知らないが、男女ともにコテコテにお白いを塗りたくるようになる。そのお白いにしても、鉛成分が含まれており肌にいいはずがなかった。しかも、乾燥するとすぐに剥げ落ちる品質の悪い代物であった。もし面白いものなどを見て笑おうものなら、たちまちボロボロとお白いが剥げ落ちるので、特に女性の場合は常に無表情でいることを強要された。そのため、手には絶えず檜扇(ひおうぎ)というものを持ち、笑い出しそうになったり、急に表情が崩れそうになると即座にそれで顔を隠したのである。当然のことながら、檜扇はなくてはならぬアイテムとなった。 |
|
| 着るものにしても、十二単(じゅうにひとえ)と言ったたいそう豪奢で凝ったつくりのものになっていくのだが、十数枚も重ね着をするわけで、暑さ十数センチにもなり、夏でなくともむせかえったわけで、体臭が臭わなかったはずはない。その臭いをごまかすためか、香がいつも炊き込まれていたらしい。 |
|
| このように、美意識の基準は大きく変わり、特に、女性の場合は、髪が長くて艶があることがまず挙げられるようになる。髪の長さは平均で3メートル以上はあったと思われているが、髪を洗う習慣はなく、沐浴(もくよく)時においてぐらいであった。しかし、その沐浴にしても、5か月に一度ぐらいしかなかった。 |
|
| 眉にしても、自毛のまゆ毛はすべて引っこ抜き、本来、眉のある位置よりも上に棒眉と言った形状の眉を描くようになる。目と眉毛の位置がかなり離れるために、遠目にもコントラストがついて分りやすくなるが、近くから見ると、幻想的で異様な感じに見えたに違いない。しかし、それが美人の条件で、眉と目が離れていればいるほど美しいとされるのである。また、女性は10才頃になると、お歯黒と言って歯を黒く染めたが、これは白い歯は目立ち過ぎて気味が悪いというおかしな美意識によるものであった。 |
|
| こうして、平安時代の美人である条件は、中期になると、ただの容姿のみが美しいというのではなく、それ以外の要素の方が外面の美しさよりも、むしろ高い比重を持つようになっていくのである。 |
|
|
* 小町を絶世の美女にしたもの * |
|
|
|
 |
|
そういう意味からか、小町の美人伝説を生み出したのは、この頃の歌人、紀貫之の彼女に対する評価が第一の原因だと考えられる。
|
|
| 紀貫之は、平安中期を代表する歌人で、小町を絶賛して六歌仙の一人に選び、また20首近い彼女の歌を自ら編纂した古今和歌集に納めたのであった。 |
|
| 六歌仙を選んだのは紀貫之自身によるものだが、その中で、彼は、小野小町の歌を評して衣通姫(そとおりひめ)と感じが似ていると感想を述べているくだりがある。 |
|
|
紀貫之、平安中期を代表する歌人(872~945) |
|
小野小町は、いにしへの衣通姫の流なり。あはれなるやうにて、
強からず。言はば、よき女の、悩めるところあるに似たり。強
からぬは、女の歌なればなるべし。(紀貫之)
|
|
|
|
| 衣通姫とは、日本書紀や古事記で登場する古代美人で、「和歌三神」の一人に数えられているほどの和歌の名手であったと言われている。また、あまりに美しい女性であったため、その美しさが衣を通してあらわれたほどの絶世の美女でもあったらしい。紀貫之は、小町の歌をか弱くも美しい女心を歌った点で衣通姫の歌と同じような感じがすると感想を述べただけであった。つまり、小町の歌を評しただけで、小町が美女であったなどとは一言も言っていないのである。だいたい、貫之は小町よりは80年も後の時代の人間で小町とは会うことすらなかったのだ。 |
|
| 要するに、この文章が誤解されて、歌の作者であった小町本人が衣通姫と似ていると解釈されていったと思われるのである。 |
|
| こうして、小町美人伝説は急速に広まっていくことになる。そして、長い年月を重ねる間に、尾ひれも付け加えられて小野小町は、絶世の美女であり、深草少将が、彼女に拒絶され続けても、百夜の間、欠かさず小町の屋敷を訪ねたと言う物語まで創作されるに到ったのである。言わば、紀貫之の書評こそが、後世の伝説を生み出す原因となっていると思われるのだ。実際のところ、小町が絶世の美人だったという確実な証拠は何一つない。
|
|
|
* 小町は権力争いの犠牲者だった * |
|
|
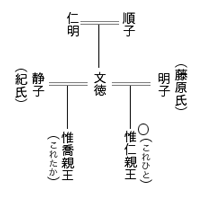 |
|
また、六歌仙に選ばれた人たちは、その内情を見ると、左遷され失脚している立場の人ばかりである。 |
|
|
当時、文徳(もんとく)天皇が治世にあたっていたが、天皇には長男の惟喬(これたか)親王と次男の惟仁(これひと)親王がいた。単純に考えれば、長男の惟喬親王が天皇になる予定だったが、惟喬親王の母方が、紀氏(きのし)だったのに対し、次男の惟仁親王の母方は藤原氏だった。 |
|
|
| 当時、藤原氏は、大変な勢力を持っており、そのために、圧力がかかり、次男の惟仁親王が、次期の天皇の候補となったのである。 |
|
| それと同時に、惟喬親王側にいた貴族らは、次々と地方に飛ばされ、失脚の憂き目にあったのである。六歌仙の一人、文屋康秀(ぶんやのやすひで)も、三河の三等官として左遷されている。同時期、小野小町も失脚したと見えて、お互い慰め合うような和歌を交わしている事実でもこのことがわかる。
|
|
|
わびぬれば 身を浮く草の 根を絶えて
さそう水あれば いなむとぞ思う
( 根無し草のように、フワフワと目的もなく生き甲斐のない日々を
過ごしておりますので、お誘い下さればともに行きたい心境です )
|
|
|
| 一方、政権争いに破れた惟喬親王の方はというと、政治の表舞台から姿を消さねばならず、泣く泣く滋賀県の山奥に隠棲せねばならなかった。彼が隠棲した地は、小野氏のゆかりの地であった。そこには小野篁(たかむら)神社というものが今でもある。小野篁は小町の父か、祖父だと言われている人である。つまり、これを見ても、小町は、惟喬親王サイドにいたわけで、彼女が政治の駆け引きによる影響をもろに受け、その結果として失脚していったと考えられるのである。つまりは彼女は政権闘争の犠牲者でもあったのである。 |
|
|
| そして紀貫之自身も、紀家の人間であることから、六歌仙を選ぶにあたり、半世紀ほど前に、辛酸をなめさせられて政治の表舞台から消されていった同胞に対する憐憫の情も加わっていることは否めない。言わば、同情票のようなものであると考えられるのである。 |
|
その後、失脚してパッとしなくなってからも、小町は後宮としてかつて仕えた仁明天皇を裏切らまいと律儀に男たちの誘いを断り続けたのではないだろうか?
そうした、彼女の頑な態度に業を煮やした男たちのやっかみが、鼻持ちならないイヤな女のイメージを作り上げ、彼女の落ちぶれた半生をさらに壮絶なまでに輪をかけて惨めな様に変えていったと推測出来るのである。 |
|
|
|
* 虚像の価値はいかほどのもの? * |
|
|
| 大阪城落城のヒロイン千姫が、妖艶で淫奔な悪女であったかのような伝説が生まれたのも、彼女が当時住んでいた江戸城の一角、吉田御殿の井戸から、わけのわからない人骨が多数発見されたことに端を発している。千姫は欲求不満のあまり、夜な夜な男を求めては、弄び飽きては殺し飽きては殺し、その亡がらを井戸に投げ込んで次々と男漁りを続けたというのである。しかし事実は出土した人骨はかなり古いもので、彼女とは全く関係がなかった。淫乱な悪女というイメージは、後世の人が勝手に想像してでっち上げたものだったのである。つまり彼女は、とんでもない濡れ衣を着せられたことになる。
|
|
 |
|
|
逆に、小野小町の場合は、権力闘争の犠牲となり、人生の後半は、ツキにも見放され恵まれない状態で寂しく一生を終わっていったかもしれないが、後世の人から絶世の美女の代名詞のような評価を得たのだから、きっと天国でほくそ笑んでいるにちがいない。 |
|
|
| それは貧困の中で死んでいった名もない画家の作品が、その後、何世紀も経ってから途方もない価値がついたようなものとよく似ているような気がするのだ。 |
|
|
| いつの世にも、スキャンダラスな噂や刺激的な伝説は、人々の食指を動かす存在である。人々によってつくられた虚像は、いずれ一人歩きしていくが、一方、人々の方も、いつしか本物と思い込み執拗に追い続けていくことになる。 |
|
|
トップページへ |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|