
真田の抜け穴伝説
〜狙うは家康ただひとり!〜
〜狙うは家康ただひとり!〜

「ようし、銃を貸せ!」部下に手渡された銃を取ると幸村は大きく深呼吸した。しくじってはいけないのだ。チャンスは一度限り。

いかに相手が大軍であっても、この大坂城を落とすことは出来ないだろう。そう誰もが考えていたのだ。しかし、天下の巨城と謳われた大坂城にもただ一つと言われる弱点があった。それは、城の南側にあたる二の丸付近の守りが手薄であったということである。


ただ言えることは、意表を突く意外な戦法を得意とする真田にとって、からくり仕掛けや抜け穴などを使って敵を翻弄することは朝飯前であり、こうした事実が伝説となって語り継がれるようになったのではないかと思われるのである。つまり伝説には、真実の核心が秘められている可能性があるということなのである。
江戸時代の講談にも、幸村が徳川の本陣まで忍び寄り、背後から家康を狙撃したという話が残されている。
「ダーンッ!」つづいてもう一発。別の兵士が首をかきむしる仕草をして落ちていく。「ダーンッ!ダーンッ!」今度は暗闇で何十もの銃火が一斉に吹き上がった。たちまち十数人の兵士が倒れて折り重なる。
結局、この日の戦闘だけで、徳川軍は死傷者1万5千という大損害を出した。家康は各武将を召集し、今後は銃弾よけの盾や竹束なしには行動してはならぬと厳令したという。
それにしても、ことごとく裏をかくような戦いぶり、心理を見透かしたような戦法をとる敵の攻撃に、家康はくちびるを噛みしめる思いであった。
「真田でございますが」「どちらだ?昌幸か、せがれか?」「左衛門佐でございます」それを聞いた家康は一瞬、ほっとしたような表情になった。しかし次の瞬間、ふたたび困惑したような表情に変わった。というのも、そのわずか数時間ほど前に、何者かによって銃撃を受け、家康は九死に一生を得て神経過敏になっていたからだ。

つまり出城をあっさり放棄した理由は伏兵をしのばせることにあったのである。若い秀忠はそこまで読むことは出来なかったのである。
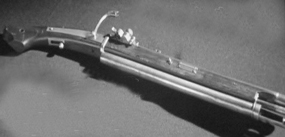
このとき家康は自決を覚悟したらしいが、部下にいさめられてかろうじて逃げおおせることが出来たと言われている。この夏の陣で壮絶な突撃をした真田幸村は、敵からも日本一の将として絶賛されることになった。
また、島原の乱が勃発した折は、天草四郎は秀頼の嫡男に違いないなどと言われたりした。秀頼や幸村の死を信じたくない庶民は、その後もことあるごとにいろいろと噂し、いつしか噂はこうした伝説に形を変えていったのだという。
「猫の首」小松左京 集英社文庫