
狼に育てられた少女
〜狼っ子・アマラとカマラの記録〜
〜狼っ子・アマラとカマラの記録〜

次に紹介する話を読む時、我々は「三つ子の魂百まで」という諺をあらためて思い起こさざるを得ない気持ちになってしまうだろう。










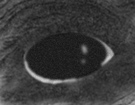
「この母親狼は、きわめて崇高な愛情を持った理想的な優しい母親に違いない。人類の感情に勝る高貴な感情がこの動物の心の中は宿っている。人間の子供を養育し、共に生きようとする事実をどう解釈すればいいのだろう。きっとそれは神の御心によるものであるとしか考えられない・・・」
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップナビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
狼に育てられた少女
〜狼っ子・アマラとカマラの記録〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 狼に育てられた人間の子供 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界史上に名高いローマ帝国を建国した二人の創始者、ロムルスとレムスが、狼の乳で育てられたという伝説は有名である。神話の世界では、動物に育てられたという話は多い。しかし、これまで、そうした話は神話上での話で現実にはあり得ないものだと考えられていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし現代になると、人間の子供が野生の動物に育てられたという話が次々と報道されるようになった。中には、十分な証拠や証人も揃えられ、そうした話はもはや、つくり話ではなく歴然たる事実であるということが信じて疑われないようになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりわけ19世紀頃から、インドやベンガル地方で狼に育てられたという子供の話が多数報告されるようになった。その中でも、ミドナプールで発見された狼少女の話は記録にも詳細に取られ、世界中に紹介されて多くの人々に衝撃を与えた。それは、まさに信じられない驚愕すべき出来事であった。つまりこの記録は、狼によって育てられた人間の子供が、その性格や習慣、身体的特徴までもが狼のようになってしまうという事実を如実に我々に示したものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録によると、彼女らに刻み込まれた狼特有の特徴は、人間社会に引き戻された後も、死ぬまで決して消えることはなかったのである。そして、狼少女から人間への復帰は、まさしく彼女らにとって、大変な苦痛と努力を強いる結果となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次に紹介する話を読む時、我々は「三つ子の魂百まで」という諺をあらためて思い起こさざるを得ない気持ちになってしまうだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それは、彼女らのためと信じて、無理やり人間社会に引き戻したことが、果たして本当に幸せであったのか疑問に思われて来る内容であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ帝国をつくったロムルスとレムス。英雄が野生の動物によって育てられたという話は神話の世界では多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 恐ろしい話 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 話は今から90年ほど前までさかのぼる・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920年、孤児院を営むシング夫妻は、受け持ち地区を定期的に回り、伝動活動を続ける宣教師でもあった。夫妻はゴダムリという村を回った時、村人から恐ろしい話を聞かされた。それは村のはずれにある白蟻の塚の近くの洞穴に、世にも恐ろしい化け物が出没するというのである。その化け物は夕暮れ時に出没する事が多く、その話っぷりから村人たちがその化け物をいかに恐れているかがうかがい知ることが出来るものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして、村人たちは、牧師夫妻にその化け物を何とか退治してくれることを期待しているようであった。もしそれがだめな場合、彼らは長年、住み慣れた土地を捨ててでも、この恐怖から逃げ出したいと考えているようであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこで、シング牧師はその話が真実かどうか確かめることにした。そのため、例の洞窟から百メートルほど離れて立っている大きな木に、観察用の見張り台を設置することにした。見張り台は、外からわからぬように板べいで囲い、その中に入って双眼鏡でこっそりと見ようというのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング牧師が見張り台に入って、1時間ほど経ち夕暮れ時になった頃、まず大きな狼が1匹その穴から飛び出して来た。続いてもう1匹。彼らは出て来るなり異常がないか臭いを嗅ぎ、周囲をうかがっているように見えた。恐らく最初に出て来た狼は母親だったと思われた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まもなく、子供の狼が2、3匹連れ添うように出て来た。そして、それに連なるように、奇妙な生き物が2匹穴から這い出して来た。それは茶褐色の肌をしており、髪は肩あたりまで垂れ下がっており、目は鋭い輝きを帯びてまるで狼の目のようであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それは、穴から出て来るなり4つ足でそこら中を素早く走り回っていた。シング牧師は、その時、この不気味な生き物こそ村人を恐怖に陥れている化け物の正体に違いないと考えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしまもなく、牧師はそれが人間の子供ではないかと確信を抱き始めていた。確かに、その化け物は、一見、この世の物とも思えぬ奇怪でグロテスクな生物のようにしか見えなかったが、牧師には人間の子供のように見えて仕方がなかったのである。そうして、出来るなら救い出して人間として育ててやりたいと考えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1週間後に捕獲作戦は行われた。まず、巣にしている巨大なアリ塚を取り囲むと、男たちがシャベルを突き立てて掘り進んだ。すると、いきなり1匹の狼が穴から飛び出して来た。その狼は、怯えたようにジャングルに一目散に逃げ込んで行った。続いてもう1匹あらわれたが、それも脱兎のごとくジャングルに消え去った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、三番目に現れた狼は違っていた。その狼は、他の狼たちのように逃げようとはせず、そこを立ち去ろうとしなかったのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それどころか、男たちに向かって突進して、彼らを四方に追い散らすと、穴に飛び込んだりした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再び現れると、今度は、歯をむき出し、荒れ狂ったようにうなり声を上げて、頭を下げ、耳を後ろに寝かせ、威嚇するように尾を激しく左右に振り鳴らし、地面をひっかきながらそこら中を走り回った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング牧師は、この時、この狼こそ母親だろうと思った。その行為は、まるで自分の巣と子供たちを自らの命を張って懸命に守ろうとするように映ったからである。狼の健気な姿に心を打たれた牧師は、何とか生け捕りにしたいものだと思った。しかし、そうした牧師の心とは裏腹に、次の瞬間、男たちはこの母親狼を情無用とばかり矢で射殺してしまった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母親狼を殺してしまうと、男たちは、再び、洞穴の入り口を掘り出した。すると、たちまち、回りがすべて倒壊してポッカリとほら穴の奥までが見渡せるようになった。一番奥の隅っこに二匹の子供狼と二匹の得体の知れぬ奇怪な生き物とがからみ合って丸くなっているのが映った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、それらを引き離していく作業がこれまた大変な仕事だった。狼の子供よりも化け物の方が凶暴で、恐ろしい形相で歯をむき出すと、立ち向かって来ると思えば戻ったりで、そして、再びかたまり合ったりを繰り返すのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、所詮、男たちにかなうはずもなく、大きな布を被せられては、一匹ずつ引き離され、布で縛り上げられてしまった。こうして、奇妙な捕り物劇が終わると、牧師は男たちに日当を支払い、二匹の子供の狼は、市場で高く売れるというので男たちに与えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 獣のような驚くべき特徴 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕らえられた化け物の正体は、何と1才と8才ほどの二人の人間の少女であった。二人はおそらく姉妹ではなく、別々の時期に狼に連れ去られたと考えられた。シング牧師は小さい方をアマラ、大きい方をカマラと名づけることにした。夫妻はことのいきさつについて誰にも話すことをしなかった。秘密を知れば、迷信深い人々から忌み嫌われ、危害を加えられる可能性があったからだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の少女はこうして人間社会に引き戻されることとなった。二人の身体は、最初、汚物と泥にまみれ狼特有の臭いが染みついていた。しかし、水浴して凄まじいばかりの髪の毛の固まりを切り取ると、どうやら人間の子供らしい容貌になった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のうち、少女たちは恐怖を除いては人間らしい感情をわずかも示さなかった。何事にもひどく無関心で、部屋の片隅にうずくまったまま、何時間も同じ姿勢を取り続けたのである。こうした行為は居心地のいいジャングルから連れ出され、仲のいい子供狼もいない環境に置かれたために、心を悩ませてホームシックのような状態になったと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体的に、普通の子供たちと決定的に違っていた点は、あごの骨が非常に発達していたことであった。そのため、顔の輪郭そのものの形が変化していた。関節も長い間、四つ足で歩いていたために柔軟力を失って、立ち上がることは出来ず固いマメでおおわれていた。ゆっくりと移動する時は、手と膝のみを使って進むのである。早く移動しようとする時は四つ足になった。その時の速度は大人にも追いつけぬほどのスピードであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動面は、まさしく狼そのものと言ってよかった。日光を嫌い夜行性で、昼のうちは二人で重なるように暗い場所で眠る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足をちぢめ膝は胸に引きつけて、その姿はまるで子犬が重なり合って眠っているようであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方になると、少女たちは元気づき大胆となる。そして、4本足で活発に走り回り遠吠えさえするのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重なり合って眠るアマラとカマラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特に夜の12時頃を過ぎようものなら、カッと目が見開かれ、ネコのように青いギラギラとした光を帯び、真っ暗な中でも物が識別出来るのである。しかも信じられないほどの嗅覚と聴覚を持っており、約60メートルも離れた距離から生肉の臭いを察知するほどだった。そしてどれほど離れていようとも、人のほんのかすかな足音でも聞き分けることが出来るのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少女らの好物は、生肉や牛乳で、ニワトリの内臓などは手を使わずに直接口だけで食べた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水や牛乳などは、ピチャピチャとなめるが、こうした食べ方は、狼との生活によって得た習慣だと思われるものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狼少女の食事風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、何か臭いの異常に気づいたり、物や人間の存在を確かめようとする時は、いつも鼻を宙にあげてクンクンとさせて、その方角を嗅ぎ付ける。また食べ物を食べる時も、必ず食べる前に臭いを嗅ぐが、そうした仕種は狼そのもののように見えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 人間として目覚める * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒さや暑さと言った感覚には鈍感で、夏でも冬でも裸で動き回ることを好んだ。衣服を着せようとすると、いやがり、ズタズタに噛み裂いてしまうのであった。大変寒い日でも、何も身につけようとせず震えることもなかった。 |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング牧師は、こうした彼女らを何とかして人間社会に馴染ませようと試みた。そのためには、彼女らの夜行性と生活リズムを断ち切らねばならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこで、まず、手始めに、彼女らを日の照る場所に連れ出し健全な昼の生活に慣れさせようと考えたのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少女らは、フンドシをだけを着けていた。取り外せないように後ろで縫いつけられていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしすぐに、牧師には少女たちが直射日光には耐えられないことがわかった。長時間、日光を浴びると呼吸が苦しげになり、物もよく見えず目も開けていられない様子になることがわかったのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それでも数カ月もすると、少しずつではあったが、アマラとカマラは、シング夫人には心を開くまでになっていた。最初、人間に対して嫌悪感しか持ち得なかった少女たちに心の変化があらわれてきたのだ。それは夫人の誠実さと母性愛から来るものであった。自分を愛してくれるということを知った時、そこに揺るぎない信頼関係が生まれる。つまり、愛情を理解して、相手を信頼することが出来た時に、人間としての成長が始まるのであろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング牧師はこの時、愛情こそが彼女らの意識の下に眠っている人間性を呼び起こすものだと確信した。相手がネコや犬と言った動物なら、飼い主とペット程度の友情で終わったかもしれない。しかし、少女たちは真の人間として、今後さらにそれ以上の深い成長を遂げることが出来るはずであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、運命とは時として残酷な結果を持たらすものである。人間の社会に連れ戻されて1年ほど経った頃、二人の少女は、突如、恐ろしい赤痢にかかってしまったのである。発病して、5日間、彼女らは意識を失ったままであった。夫人は、この間、ずっと彼女らに付きっきりで看病し続け、シング牧師も、毎日、朝も夜も枕もとで祈りを捧げていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何日か経つうちに、カマラの方は次第に快方に向かっていったが、しかし、体力がなく小さいアマラには耐えうるには難しい状態であった。そして、ついに絶望的な事態が訪れた。アマラは痙攣を何度も繰り返すようになり、心臓は激しく鼓動を打ち、脱水状態から、体は見る見る衰弱していったのである。血の気がなくなった彼女は顔面蒼白となり、苦しげに喘ぐ息づかいからは、誰が見てもアマラの死が間近に迫っていることが理解出来た。そして、発病から2週間後、アマラはロウソクの炎が消え去るように息を引き取ったのである。それは1921年9月21日の出来事であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマラが死んだ時、カマラは、最初、死という概念が理解出来なかった。彼女の側にピッタリとついて離れず、懸命に体をゆすったり起こそうとした。しかし何度試みてもアマラはピクリとも動かなかった。そのうち、アマラの体が急速に冷たくなっていった。その時、本能的にアマラが死んだと悟ったカマラは始めて涙を流した。両方の目から大粒の涙を一粒づつ。それは人間であるがゆえの愛する身内に見せる哀れみの気持ちだったのだろうか。それ以後、カマラは数日間は食事もせず引きこもったままであった。丸一か月間というもの、一人っきりで部屋の隅にうずくまったままだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カマラはそれから8年後の1929年11月に死んだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カマラはその間、他の人間たちにも慣れ、また、決して上手ではないものの直立歩行をするまでになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子やぎや子猫を優しく撫でる時の彼女の表情には、笑顔に近い輝きさえ見受けられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確かに、彼女は学習と努力によって、精神や人間性にずいぶん成長を見たが、その進歩は非常にゆっくりでしかなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死の間際、カマラは推定16才ほどであったが、人間の成長としては3才ほどの幼児でしかなかったと言われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング夫人からビスケットをもらうカマラ。彼女の大好物であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 狼少女は捨てられた自閉症の子供だった? * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうした事実は、我々に何を物語っているのであろうか? つまり人間に生まれても、最も肝心な幼児期にふさわしい教育と学習がなされなければ、人間になることさえ出来ないということであろうか。実際この話は、子供の誕生後の環境や教育が、その後の人間形成において、いかに大切かという例え話として、教科書で引用され掲載されたのも事実である。そして、この話がきっかけとなり、人間の悪徳や徳と言った本性が遺伝と環境のいずれかの要因によるものか議論されることにもなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし今日、世界中に衝撃を与えたこの記録の信憑性を疑う人々は多い。それどころか、一部の科学者たちは、シング牧師が幼児期における教育がいかに大事なのか戒めるために想像した作り話であるとも断言している。科学者たちはその根拠として、授乳や移動の問題などを挙げて、一連の話が荒唐無稽であるばかりでなく不可能な事柄であることを告げている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それによると、狼は積極的に子供に母乳を与えることをせず、逆に人間の乳児は乳首を口元にまで持っていってやらないと乳を吸うことが出来ないので授乳が成り立たないというのである。それに加えて、狼の母乳は人間のそれと比較してタンパク質や脂肪分が数倍も高く、成分が違い過ぎるため乳児は消化出来ずに吐き戻してしまうと指摘する。また、狼は餌を求めて移動を繰り返す習性があるが、その移動速度は時速50kmにも達し、短距離選手でさえ追いつくことは不可能に近い。従って、少女たちが彼らとともに移動出来るはずは到底あり得ないと言うのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確かに、残された記録の中にも虚言や虚飾と思われる箇所が幾つか指摘されているのも事実である。暗闇で目がギラギラと光ったり、犬歯が異常に発達しているなどという記述は、生物学的にあり得ない箇所で、牧師が人間が狼に育てられたらこうなるだろうという先入観の元でアマラとカマラの行動を解釈したとしか思えない節もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学者たちによれば、狼に育てられたという少女は、実は、親に見放されて野生に捨てられた精神薄弱か重度の自閉症(先天的に脳に障害のある病気)の子どもだったと考える方が現実的だという。つまり、こうした野生児の仕種や行動が、一見、狼によって育てられた子供のように映ったのではないかと主張するのである。確かに、インドの貧しい地方では、昔から、この種の子どもたちは、役立たずと考えられ、ある程度育てられた挙句に、親に捨てられたという悲しい歴史があるのも疑いのない事実なのである。シング牧師が、誰かから二人の少女が狼の洞穴から救出されたという話を聞き、それをさも自分の体験談らしく脚色した可能性も否定出来ないというのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうすると、アマラとカマラも、野生に捨てられた精神薄弱か自閉症の子供だったのだろうか? しかし二人の少女は、多くの写真にも撮られたばかりでなく、詳細に観察され記録として残されているのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判所には、今も当時のシング牧師の宣誓供述書が残されている。その書面には、神の御心に仕える者として、偽らざる真実のみを述べると記されているのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、牧師を個人的に知る人々は、彼の誠実さは絶対に信頼しうるものだと口を揃えて止まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シング夫妻は貧しい田舎で、長年、宣教と慈善事業に従事し、自分たちの私財のすべてを投じて孤児院を設立し、恵まれない子供たちを救って来たのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドナプール孤児院の子供たちとシング夫妻。夫妻の足下にカマラがいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうしたことから、シング牧師が自分の想像からこうした作り話をしたとは到底思えないのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 元来そなわった深い愛情ときずな * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狼に詳しい専門家は、彼らオオカミは大変家族愛の強い動物であるということを主張する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例えば、人間の手によって子供を奪われた母親狼は、毎晩のように遠ぼえを繰り返すのだそうである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その声の調子は、ひたすら我が子を慕うように心から胸を締めつけられるような悲しみに満ちた声だそうである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また母親を殺された狼の子供は、母親の体が冷たくなってしまっても、いつまでも母親の遺体から離れないとも聞く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうしたテーマを考えた場合、私は「オルカ」という映画を思い起こさざるを得ない。オルカとはシャチのことで水中を驚くべき早さで泳ぐクジラの仲間と考えてよい。しかし、その性格は肉食で海のギャングとさえ言われているほど荒々しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その反面、彼らは仲間意識が強く、非常に社会性が強い動物と言われている。例えば、餌をとるのに仲間同士で協力し合ったり、1頭が捕った獲物を他の仲間たちと分け合うこともあると言われているのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その上、シャチは大変愛情が深い動物と言われ、一夫一婦制で、一生同じ相手に添い続けるという。しかも、知能は人間並みで様々な音波を出して海中でもあらゆる意志伝達が可能だそうである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャチ、英語名ではオルカとも呼ばれる。体長10メートル前後まで成長し、雌は60年ほど生きると言われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画のあらましはこうだ。・・・体が大きくて高値で売れるシャチを獲物とするために、ある漁師が群れを追っていた。そして、彼は首尾よく群れの中の一頭にモリを打ち込んだのである。モリが深く突き刺さったシャチは、苦しみのたうち回り、耳を覆いたくなるような悲鳴を上げながら、やがて船尾のスクリュー向かって泳いでいった。それは、苦しみから逃れるために自ら死を選ぼうとしているかのようだった。たちまち、シャチの体はスクリューでズタズタに切り裂かれ、海面にはゴボゴボと血の泡が浮き上がって来た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうして、死んだシャチをウインチで引き上げてみると、突如、シャチの腹が裂けて、中から赤ん坊のシャチが次々と産み落とされ、甲板上に虚しく落下したのである。死んだシャチはもうすぐ出産を控えたばかりの子持ちの雌だったのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その一部始終を、雄のシャチは海中からじっと見ていた。海水に浸かったその目は、涙のために潤んでいるようであった。平和で楽しいひとときを一瞬に踏みにじられ、人間の手によって愛する家族を無慈悲に殺されてしまったのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
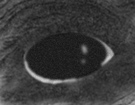 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャチの目がクローズアップされる。船上にいる一人一人の人間の顔を脳裏に刻み込んだシャチは、この時、復讐を誓った。一見、無表情に見えた黒い瞳に凄まじい憎しみの炎が燃え盛っているのを誰も知ろうはずもなく・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その時から、愛する自分の家族を殺した船員すべてに、シャチの復讐が開始されるのだ。それは想像を越えた、まさに常識という概念を超越した執念深さで始まるのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、こうした話は興味本意のストーリーで、動物は本来、本能だけで生きており、人間のような複雑な感情はないと考える人も多い。果たして、悲しみや憎しみ、愛情などと言ったデリケートな感情は人間特有のもので、動物には備わっていないのであろうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元来、動物には、予知能力や特別な直感力があると言われ、人間の理解をはるかに越えた不思議な感覚が備わっているのも事実である。そういう意味で、人間を基準にして、そうした決めつけをするのには無理がある。過程がどうであれ、貧しさ故に親に捨てられ、あるいはジャングルに置き去りにされた人間の子供が野生の動物に拾われ、命を救われて長らえることが出来たという事実に私は感動を覚える。動物には私たち人間には決して推し量ることのできない感情や特別の愛情が備わっていると私は信じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後に日記に書かれていたシング牧師の言葉を紹介しよう。 「この母親狼は、きわめて崇高な愛情を持った理想的な優しい母親に違いない。人類の感情に勝る高貴な感情がこの動物の心の中は宿っている。人間の子供を養育し、共に生きようとする事実をどう解釈すればいいのだろう。きっとそれは神の御心によるものであるとしか考えられない・・・」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||