
硫黄島の戦い
〜日米の決戦場となった地獄の島〜
〜日米の決戦場となった地獄の島〜

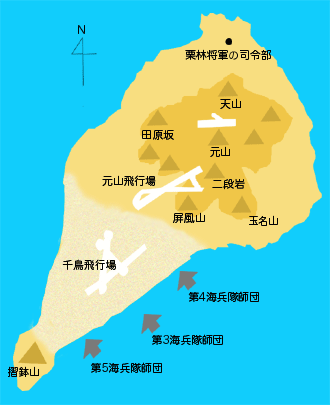




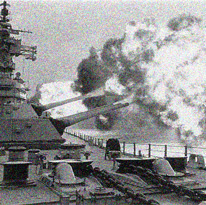

「栄えある皇軍」「天皇陛下」「神州不滅」「鬼畜米英」・・・
それらはいずれも耳にたこが出来るほど聞かされて来た言葉だ。これらは水面に浮かんで来る水の泡のように次々とあらわれては消えていった。次に彼は今自分が行おうとする行為についても考えた。

「ここが一番きつかったな・・・」


現在、硫黄島の戦没者で日本に帰ることの出来た遺骨は6千柱ほど、残る1万4千柱は今なお硫黄島のどこかの砂に埋もれたままである。
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップナビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硫黄島の戦い
〜日米の決戦場となった地獄の島〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦局も押し迫った1945年、2月16日の早朝。大平洋上に浮かぶ空母バンカーヒル上で、上陸作戦の総指揮官、ホーランド・M・スミス中将は沈欝な気持ちで双眼鏡を覗いていた。彼の視線の先には左端に小高い山があるだけののっぺりとして殺伐とした小島が映っていた。それは最も幅の広いところでも3キロほどで長さ7キロ足らずの豆粒のような孤島であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この取るに足らない小島は、東京から南へ1000キロほど行ったところにある 硫黄島(いおうとう)という火山島で、当時の航空機で片道3時間ほどの距離にあった。島の南部には標高169メートルの摺鉢山(すりばちやま)があるだけのどこと言って特色があるはずもない何の変哲もない島である。しかし、この島は今後ひと月の間、太平洋戦争の行方を決める一大決戦場となる運命にあった。全体が火山灰に覆われただけのこの島が、なぜそれほど戦略上重要だったのだろうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 嵐の前の静寂 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944年7月、サイパン島を陥落させたアメリカ軍は、この島を拠点に日本本土への爆撃を開始した。しかし、これほどの遠距離だと護衛戦闘機が随伴することは不可能だった。しかも、日本本土への出撃の際、硫黄島の上空を飛ばねばならず、察知した守備隊によって事前に通告されてしまうのだ。その結果、本土上空で待ち構えている日本軍機の死にものぐるいの体当たり攻撃で撃墜される機も多く、損傷を受けて海に着水を余儀なくされる機も多かったのである。そのため、アメリカとしては傷ついたB29の不時着できる基地がどうしても必要だったのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方、日本側も同じ理由でこの島が重要であった。硫黄島は本土を空襲してくるB29の基地を叩くための中継基地であり、この島がアメリカの手に渡れば、日本のあらゆる都市が、たちまち絨毯爆撃によって焦土と化してしまうことを知っていた。サイパンを落としたアメリカ軍はいずれこの島に矛先を向けて来ることは明らかであった。かくして、硫黄島は日米決戦の天王山となる運命にあった。やがて昭和20年1月、戦機が訪れたと見たアメリカは、大艦隊を硫黄島にさし向けて来た。その規模は空母12隻を含む戦艦など数百隻にも及ぶ大艦隊で、それはまさに太平洋を埋め尽くすほどの巨大なものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「・・・後5分でこの島への艦砲射撃が一斉に開始される。恐らく、戦艦群から打ち出される40サンチ級の凄まじい砲弾の嵐はこの島をことごとく粉砕するであろう」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「我が海兵隊の損害を最小にとどめるためにも、是が非でも徹底的にたたいておかねばならん。タラワ、ペリリュー、サイパンの時のような損害だけはどうしても避けねばならない」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スミス中将は腕時計を見ながら、過去の忌わしい戦闘となったシーンを脳裏で描いていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上から見た硫黄島。左端に標高169メートルの摺鉢山が見える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それからきっかり5分後だった。大音響とともに硫黄島に向けて艦砲射撃が行われた。それは、凄まじいばかりで3日間も続いた。盲めっぽう撃たれた砲弾数は実に数十万発に及び島中いたるところに落下した。その恐るべき破壊は丸3日間も続いた。1平方メートルに10発という凄まじいものであった。3日目にはサイパンから飛んで来たB29爆撃機の編隊が上空から爆弾を投下した。駆逐艦は沿岸部まで接近してあらゆる火砲を使って砲弾を撃ち込んだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうした海と空からの交互の攻撃は苛烈をきわめ、海岸線の砂浜はほじくりされ、跡形もなく吹き飛んだ。摺山に至っては、頂上の4分の1ほどが吹き飛んで外形すら変わり果ててしまった。この頃になると、沈欝だった中将の気分も幾分か楽観的なものになりかけていた。この分では仕事は早めに終わるかもしれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 猛烈な反撃 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目の早朝、100艘ほどの上陸用舟艇の第一波が、横一線にならんでわずか幅4キロほどの砂浜目指して殺到して来た。海兵隊のある兵士は、もはや生存者はほとんどいないかもしれないと思ったという。また俺たちの仕事のために少しはジャップを残して置いてもらいたいものだと豪語した兵士もいた。事実、それほどまでに凄まじい砲火だったのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
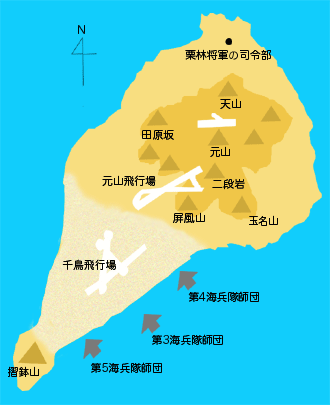 |
海兵隊の誰もが少しばかりは日本側の抵抗があるものと予測していた。ところが、海岸に到達しても、海岸は恐ろしいほどの静けさで生気というものを全く感じさせないのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭上には硝煙の立ちこめる中、ギラギラする大陽が容赦なく照りつけるばかりであった。海兵たちは拍子抜けしてしまった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞こえて来るのは打ち寄せる波の音だけで、時おり、散発的に銃声がするが、とても反撃の比ではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やはり、あれほどの艦砲射撃で、日本軍のトーチカや機銃座はことごとく吹っ飛ばされてしまったのだろうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この分では、5日ほどでこの島を占領出来ることだろうと海兵隊の誰もが楽観的な気持ちになりかけていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ軍は1波1200名ほどの海兵隊員を5分間隔で8回繰り出し、40分足らずの間に9千名の兵士を上陸させる計画であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸線には次々と上陸してくる上陸用舟艇や水陸両用トラックなどで身動きが取れないほどになって来た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2時間後には9千人という大勢の兵士が上陸し、大量の物資が陸揚げされた浜辺はたちまち前進基地の様相を呈して来た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄島に殺到する上陸用舟艇の群れ。左端に摺鉢山がかすかに見える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいした攻撃がないと見た海兵隊は、前進を開始しようとしたまさにその時だった。突如、上空から怪鳥の鳴くような音が幾つも聞こえて来たと思った次の瞬間、大地を覆すような大音響がして、10人ほどの米軍兵士がバラバラと一固まりになって空中に吹き上げられた。それと同時に前方の無数の岩陰から金属的な破裂音がしてぱっぱっぱっと数十の砂煙りが立ち上った。日本軍の重機関銃が一斉に火を吹いたのだ。あっと言う間に5、6名の兵士がなぎ倒された。全員即死だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それは、まるで嵐が来たようであった。凄まじい機関銃と爆弾でアメリカ軍はたちまち、大パニックに陥った。一体全体何が起きたのかわからなかった。頭上ではひっきりなしに、ヒィーンという金属音を響かせて何かが降って来る。それは、彼らがこれまで経験したこともないような攻撃だった。降って来る爆弾は、見たこともないような巨大な爆弾で、地面に落ちるとズシーンと腹の底に応えるような地響きがした。その度に、ものすごい爆風が起こり、兵士と言わず物資と言わずそこら中のものすべてが空中高く吹き飛ばされるのである。悲鳴を上げようが、逃げる場所などどこにもなく、ところ構わず落ちる巨弾にたちまち海岸は死体で埋め尽くされた。海水は真っ赤に染まり、もげた手足、胴体の一部、内臓らしきものが砂浜に打ち上げられている。こうして、上陸後数時間も経たないうちに千名ほどが死傷し阿鼻叫喚の地獄絵図を現出した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上陸部隊から信じられないほどの猛烈な攻撃を日本軍から受けている。戦車の支援が必要だ。戦車を頼むという悲痛な連絡が飛び込んで来た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それを耳にしたスミス中将は愕然とした。やはり、日本軍は壊滅などしてはいなかった。砲撃で弱まっているどころか、何でも食べ尽くす貪欲な胃袋のようなものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかもこれまでの戦闘とは全く違うものだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本軍の反撃始まる。砂浜から身動きの取れなくなったアメリカ海兵隊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体、ここを守っている日本軍はいかなる部隊なのか? そして、この日本軍を率いているクリバヤシなる指揮官は何者なのだ。硫黄島守備のために本土から派遣されて来たというこの指揮官に、アメリカの情報部は警戒の念を強めていたが、とりたててそれ以上の関心を払うこともなかった。スミス中将はそのことを今さらのように悔やむと宙を見据えて唇をかみしめた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 死にものぐるいで陣地を構築 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944年6月、大本営からある一人の将軍が派遣されて来た。その将軍の名は、栗林忠道(くりばやしただみち)陸軍中将。アメリカとカナダに駐在経験があり、アメリカ人の気質を知り尽くしていた数少ない陸軍将校の一人であった。その上、彼は徹底的な合理主義者で有能な戦術家でもあった。栗林はアメリカ人を尊敬してはいたが、戦争となれば、出来る限りアメリカ人を殺傷して本土決戦の時間稼ぎをする以外にないと心に決めていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイパン、グアム、ティ二アンなどの守備隊が水際決戦で破れていたことに教訓を得た栗林は、敵にいったん味方のふところ深くにまで飛び込ませ、敵との距離を狭めておいてから一挙にたたき潰すという戦術を考案していた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵味方の距離が接近すればするほど、敵は同士討ちの危険からアメリカお得意の派手な援護射撃が出来なくなるからだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのためには、敵が上陸して来るまで戦力を温存せねばならず、猛烈な艦砲射撃と爆撃に持ちこたえることのできる頑強な陣地が必要であった。こうした理由から、洞窟陣地を構築して島全体を要塞化し、地下から強大なアメリカ軍を迎え撃とうと考えたのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗林忠道(1891〜1945)長野県で生まれる。日米からも名将としての誉れが高い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼の要請のもと、大本営から大量のセメントや資材、削岩機、陣地構築の専門家などが送られて来た。しかし、岩と火山灰だらけの殺風景きわまるこの島で、洞窟を掘ることは大変な労力が必要であった。わずか1メートル掘るだけでも熱気と硫黄ガスが噴出した。そのため作業には防毒マスクが必要でそれもせいぜい5分間しか続けられなかった。兵士には7割の時間を陣地構築に裂くように命じた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それと同時に彼は島の民間人を本土に送還した。こうすることで、後顧の憂いなくぞんぶんにアメリカ軍と一戦を交える環境にしたのである。さらに栗林は自らの作戦に異をとなえる参謀たちを更迭し、将兵の気持ちを一つにして行くことも忘れなかった。後はどのくらい陣地づくりに時間をかけられるかで勝敗が決まるのだ。アメリカ軍が押し寄せて来るまでの時間は長くても半年ほどしかない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、工事はこの島の悪条件と戦いながら進めねばならなかった。硫黄島には一本の川もなく飲料水は雨水に頼らざるを得ない。島内に6つほどある井戸の水は硫黄分を含み、飲めばたちまち下痢をした。そのため、兵士の5人に一人は衰弱して労働に耐えることが出来ない体となってしまった。こうした苛酷きわまりない環境にもめげずに工事は昼夜を問わず突貫で続けられた。アメリカの偵察機は、日本軍の地上施設が次第に姿を消して行く事実を刻々と伝えていた。主要施設は、次第に出来上がっていく巨大な地下陣地に順次移されていたのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうして超人的な努力で完成した洞窟陣地はまるで蟻の巣のように張り巡られた地下要塞であった。地下深く穿たれた洞窟陣地は全長は26キロほどもあり、いかなる砲爆撃でも耐えることが出来た。摺鉢山の海岸部のトーチカは鉄筋コンクリートで頑強につくられ、壁の厚さだけでも1.2メートル以上もあった。機銃座に至っては、わからぬようにカモフラージュされて巧妙につくられていた。ちょっと見たぐらいでは全くわからなかった。しかも、こうした銃座が一つの場所に複数あり、それぞれが援護できる位置にあったのだ。例え、一つや二つが潰されても内部の兵員は自由に移動して別の場所から攻撃ができるのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄島の防衛線は、このように何重にも配備された地下のトーチカ陣地で構成され、さらに西中佐率いる戦車隊がこの地区を援護していた。戦車隊と言っても、車体をそっくり土砂に埋め砲塔だけ地上に出して戦うという戦法である。かなり近寄っても戦車が埋められているとはわからないほど巧みに偽装されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下要塞はアメリカ潜水艦の補給妨害に合いながらも、ほぼ予定通り完成し、敵の上陸が始まる頃には全軍が戦闘配置についたのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして、恐らく、これが最後の戦になると確信していた栗林は、敢闘の書となる6項目をすべての兵士の頭に叩き込んだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのあらましは、我らは全力を持ってこの島を守り抜かん。一発必中の射撃で敵を撃ち倒し、爆薬を抱いて敵の戦車に体当たりを行わん。敵10人を倒すまでは死すとも死せず。例え、最後の一人となろうとゲリラとなって敵を後方から苦めんという徹底した内容であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西竹一(1902〜1945)東京生まれ。華族(男爵)出身で愛馬ウラヌスを駆って1932年のロサンゼルスオリンピックの金メダリストとなる。アメリカ人を知り尽くし栗林とともに将兵の人気は高かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのために、栗林は、いたずらに戦力の消耗となる従来の玉砕戦法を禁じ、徹底的に生き抜くことで、敵を持久戦に持ち込み、本土決戦への時間稼ぎを行おうとしたのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうして栗林以下の2万4千名の日本軍守備隊は、一人十殺の誓いを立てアメリカ軍を待ち構えることになった。この時、硫黄島守備の兵力は海軍陸軍合わせて2万4千名あまり。小銃、機関銃などあらゆる火器を可能な限りかき集め、その火力は通常の部隊の3倍以上に匹敵していた。しかも日本軍は完成したばかりの新兵器、奮進砲(ロケット弾)や超大型の迫撃砲まで持ち込んでいた。最も大きいロケット弾は直径が40センチもあるゴミバケツほどの巨大な弾頭をしており、命中精度は低いものの着弾時の破壊力は空恐ろしいものがあった。これらは巧妙に岩穴に隠され、あらかじめアメリカ軍の軍需物資が山積みにされるであろう海岸部に照準されていたのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 地獄の2週間 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上陸したアメリカ軍は、その後も目に見えない相手と戦わねばならなかった。上陸した第一日目の損害は死傷者数2400名ほどにもなった。これはノルマンジー上陸作戦時における死傷者数をはるかに上回るものである。この先どうなるのか誰にもわからない。日本軍が一体どこにいて、何名いるのかすらわからなかった。突然、どこかで銃声がしたかと思うと、先頭を行く相棒が頭を撃ち抜かれてバッタリ倒れるのである。会話を交わしたばかりの仲間が、振り返ると息絶えていることも珍しくなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ軍はすでに3万名の海兵隊を上陸させていたが、そのほとんどは釘づけ状態であった。夜になると、アメリカ兵は見えない日本兵におびえ、照明弾を絶えず打ち上げ、何か物音がする度にヒステリックになって銃を盲めっぽう乱射していた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
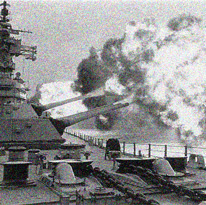 |
翌朝、小雨の降る中、アメリカ軍は摺鉢山に猛烈な攻撃を開始した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この島で最も高い摺鉢山を奪取しなければ、前後から攻撃される危険があるので、早急に落とさねばならなかったのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艦載機の攻撃は延べ数百回にも及び、海上からは数千発の艦砲射撃が摺鉢山の日本軍陣地に撃ち込まれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ軍は日本軍の陣地を発見すると、海上の軍艦や航空機に連絡して、大量の砲弾と爆弾の雨あられのごとく降らせた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上陸2日後、アメリカ軍は摺鉢山に猛烈な攻撃を開始した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうして、手榴弾を投げ込んだり、火炎放射器によって内部を焼き尽くしたりして少しづつ頂上に登り詰めていった。この凄まじい攻撃で、さしもの摺鉢山の日本軍の抵抗も少しづつ弱まって来た。わずか2日間で、1700名いた日本軍の守備隊は7割以上が戦死してしまうほどであった。そして5日目には、ついに摺鉢山がアメリカ軍の手に落ちた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、戦いはこれからであった。島の中部から北に広がる丘陵地帯は、起伏が多く地形が複雑に錯綜している場所である。ここには数百の陣地が死角のないように縦横に配置されており、まだ無傷の日本軍がアメリカ兵を殺そうと待ち構えていたのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これに対して取ったアメリカの戦法は徹底的な焦土戦術であった。火炎放射戦車を先頭に、ありとあらゆるものを焼き尽くして前進していくのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵の潜んでいそうな場所は、ことごとく焼き尽くしていった。アメリカ軍の警戒ぶりは異常とも思えるほどで、いくら焼き尽くそうが、それでも前進しなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸壁にあるどんな窪みにも、手榴弾が放り込まれ火炎放射器で焼き尽くされていった。岩穴や洞窟があると、発煙弾を投げ込んで地表に出て来る煙で出入口の位置を確かめた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルドーザーや爆弾で入口を塞いでおいてから、削岩機で穴を開けそこからガソリンを流し込んで火をつけることもあった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ軍の火炎放射器による徹底的な焦土戦術。敵の潜んでいそうな場所はすべて焼き尽くしていく。後には黒焦げになった日本兵の死体が残された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうして、中にいる日本兵を皆殺しにしていくのである。それはさながら害虫駆除のようであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある日本軍の若い将校はついに我慢しきれずに神経の糸が切れたのか、発狂して穴から飛び出した。将校は分けの分からぬ奇声を発しながら軍刀を振り回すと、シャーマン戦車の上に飛び乗った。彼は血走った目で、あらぬことを叫びながら、何度も戦車の装甲に軍刀を降り降ろした。結局、数秒後、その将校は蜂の巣にされて戦車から転げ落ちて死んでしまった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また別なある兵士は、爆弾でできた窪地に身を横たえた。そこには仲間の死体が無数に散乱していた。彼は、死体の一つの腹を裂いて贓物を取り出すと自分の腹に塗りたくった。そうして死体のふりをして敵の戦車が来るのを待ち受けた。彼は胸の上に大きな対戦車地雷を抱いていた。敵の戦車を道連れに自爆しようと考えていたのだ。ところが、いくら経っても敵はやって来ず、数時間たっても戦車も敵兵の姿もあらわれなかった。結局、日が暮れてしまい、彼はそのままの姿勢で横たわっているしかなかった。昼間の熱気に煽られ、腐乱した死体から、ものすごい悪臭が漂って来た。彼はあまりのひどい臭いに吐き毛がこみ上げて来たがそれでも我慢していた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲労と空腹から時おり意識が朦朧としながら、彼はいろいろなことを考えていた。脳裏にいろいろな言葉があらわれては消えて言った。 「栄えある皇軍」「天皇陛下」「神州不滅」「鬼畜米英」・・・ それらはいずれも耳にたこが出来るほど聞かされて来た言葉だ。これらは水面に浮かんで来る水の泡のように次々とあらわれては消えていった。次に彼は今自分が行おうとする行為についても考えた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「名誉ある戦死」「生きて虜囚の辱めを受けることなかれ」「華々しく玉砕」「悠久の大義に殉ずる」一体、これらに何の意味があるのだろうか? 敵の戦車とともに自爆することが、本当に国のためになるのだろうか? 自分は一体何のためにこの世に生まれて来たのか? 彼は数時間自問自答を繰り返した。考える時間はたっぷりとあった。夜が明けたが、依然、敵は姿を見せなかった。遠くで銃声はするが、戦線はますます自分から遠ざかっていくようであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついに、彼は立ち上がると、やにわに大きくため息をつき、自爆用の爆弾を無造作に捨て、代わりに衣服の一部を引き裂くとそれを木の枝に結んで白旗をつくった。そして、頭上に高くかざすとゆっくりと歩き出した。自爆して死ぬことの意味をどうしても見い出せなかった彼は、敵に投降する道を選んだのであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 栗林兵団の最後 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死闘は20日間にも及ぼうとしていた。日本軍はやけっぱちとも言える万歳突撃も行わず、頑強に抵抗を続けていた。しかし、アメリカ軍はその膨大な物量に物を言わせ、戦車と火炎放射による攻撃で少しづつであるが日本軍を北の端に追い詰めていった。この時、アメリカ軍は実に7万名もの海兵隊を上陸させていたのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日、栗林は1500名の部下とともに北の岬まで追い詰められていた。ここは背後を海に囲まれ溶岩が固まって出来た複雑な谷であった。この谷間は長さ700メートルほどもあり底には無数の溝が刻まれている場所である。その奇怪な景観の中で、最後の戦いが始まろうとしていた。もう日本軍に後はなかった。アメリカ軍はバズーカ砲を撃ったり、火炎放射器を使ったりして、少しづつ司令部に肉薄して来る。最後が近づいて来たことを悟った栗林は、ついに軍旗を焼くことを決意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月14日、栗林中将は洞窟で彼の故郷、長野の少年少女たちが歌う硫黄島守備隊の歌を聞いていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄島の戦いは今や最終局面をむかえていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月17日の夜、栗林は大本営に最後の電報を打った。今や弾丸尽き、水枯れ、全員反撃し最後の敢闘を行わんとする。皇国の必勝と安泰とを祈念しつつとこしえにお別れ申し上ぐというものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、硫黄島から200キロ離れた父島の将兵にも別れの電報が打たれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗林将軍は地下の洞窟から別れの電報を発した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「父島の全将兵のみなさん、さようなら・・・」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗林の最期に至っては、米軍との最後の総攻撃を指揮し、最後は自ら数百名の先頭に立ち突撃を敢行して戦死したと言われるが、その最期については誰も知る者はない。1932年のロサンゼルスオリンピックの馬術で金メダルを取り、国民的英雄だった西中佐は愛馬ウラヌスのたてがみを胸のポケットに抱いて壮烈な戦死を遂げたと伝えられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 壮絶な戦いの後 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくして凄惨をきわめた硫黄島の戦いは終わった。しかし、アメリカ軍の受けた損害もまたひどいものだった。海兵隊第5師団第2大隊など死傷率が100パーセントだった。ある中隊では中隊長が次々と戦死してしまい、その都度7人も交替したほどであった。また、ある小隊では小隊長が5人も代わった。4人目の曹長が戦死すると5人目は少尉が代行した。しかしその少尉もまもなくなく死んでしまった。6人目は必要なかった。なぜならば、その小隊は全滅したからである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝砲の轟く中、アメリカ軍は硫黄島占領の式典を行った。将軍たちと各師団長が並び、式辞が読み上げられるとラッパが鳴り響き星条旗がスルスルと旗竿を上がっていった。式典は終わっても、誰一人として口を聞く者はいなかった。士官も兵士も重い足取りのまま黙って歩いている。式典の行われた向こうには、海兵隊兵士の墓場が彼方まで広がっているのが見えた。スミス中将は目に涙を一杯溜めていた。そして、一言つぶやくように言った。 「ここが一番きつかったな・・・」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日、栗林忠道は最有能な名将として敵国であるアメリカからも絶賛されている。物資、装備全てに圧倒的で数でも遥かに上回る三倍以上のアメリカの海兵隊を向こうに回し、最後まで互角以上に渡り合い、一ヶ月以上もこの島に釘づけにしたのであった。これは栗林自身も想像できぬほどの善戦であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
2万1千名のうち、2万名が死に、捕虜となったのはわずか9百名足らずであった。一方、上陸したアメリカ軍は、日本側を上回る損害を出した。死傷者数は約2万8千名(戦死は7千名)にも及び、これはアメリカ海兵隊史上最大の損害であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負傷して病院に収容されたアメリカ兵の多くは、戦闘が終了した後も手当てのかいなく死亡した。これは日本軍の超重砲やロケット弾がいかに彼らに重大な致命傷を与えたかを証明するものであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄島の戦闘が終わった後、アメリカ軍は、今後、日本を攻撃する進路上に彼のような指揮官がいないことをひたすら祈ったという。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負傷者を手当てする海兵隊。その多くは帰らぬ人となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 泣き崩れるかつての兵士たち * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦後、硫黄島には元兵士やその遺族たちによって、永久に後世に伝えるための記念碑が建立された。1985年には、元日米兵士による最初の戦没者合同慰霊祭も行われている。日米双方の元兵士たちは複雑な心境で、40年前に殺し合ったかつての敵と対面することになった。彼らは摺鉢山のふもとにある砂丘の上で再会した。そこはかつて40年前にアメリカ海兵隊が上陸した砂浜であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海兵隊の元兵士は、やって来るまで疑心暗疑の連続だった。あの阿修羅のような日本人と本当に心の交流が成り立つのかとさえ思った。しかし、会ってみると、日本人も同様に心に深い傷を負ってこれまで生きて来たことを知った。言葉など通じなくても、目を見るだけで相手の心が分かるのである。その元兵士は談話しているうちに、急に涙がこみ上げて来るのを止めることが出来なかった。40年前、私はこの島にジャップを殺すためにやって来た。今は殺し合ったことを心から悔やんでいる。この瞬間、私の日本人に対する恨みは消えてなくなった。彼は涙を拭うとかつての敵兵だった日本人と無言で肩を抱き合った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別な兵士だった者は言う。私の心は40年間もこの島に留まったままだった。ここにはともに戦った多くの戦友の魂が眠っているからだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回、ここに来たことで長年の胸のつかえが降りたようだった。私の仕事は今ようやく終わったのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうして、かつて、太平洋の孤島の砂浜を血に染め、生と死のはざまをさまよって殺し合った双方の兵士たちは、肩を抱き合い手を取り合って涙を流した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄島の戦闘で死んだ海兵隊の墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現在、硫黄島の戦没者で日本に帰ることの出来た遺骨は6千柱ほど、残る1万4千柱は今なお硫黄島のどこかの砂に埋もれたままである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我々は、勇気と名誉をもって戦ったこれらの人々の尊い犠牲のもとに今日の平和が成り立っていることを常に心に刻み込まねばならない。二度とこのあやまちを繰り返す事のないように。そして、いつの日か恒久の平和が訪れることを祈りながら・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||